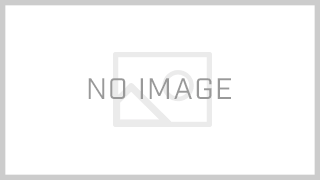コードトーンを練習して感じたこと3選!

現在ジャズギターを練習しており、アドリブを弾けるようになりたくて約半年ほど前からコードトーンの練習をしています。
ちなみに、実際の演奏でアドリブができるレベルには達していません。
そこで感じたことをデメリットも含めてまとめてみましたので、参考になれば幸いです。
コードトーンとは?
コードトーンとは文字通りコードの音を演奏することなのですが、よく混同しがちなのがスケール(音階)です。
両者の違いは「ドレミファソラシド」と弾くとスケールになり「ドミソシ」と弾くとコードトーンになる点です。
かなりざっくりした説明なので、もっと詳しく知りたい方は音楽理論の本などを読んでみて下さい。
コードトーンを練習して感じた点は以下の3つです。
① 1人でも起承転結のある演奏ができる。
② 指の動きが複雑。
③ 指板上の音名を意識するクセがつく。
感じた点①
1人でも起承転結のある演奏ができる。
YouTubeに合わせて弾いてると気にならなのに、何も鳴っていない状態で弾くと同じフレーズでも何か違和感がある。
こんな風に感じたことはないでしょうか?
通常の楽曲はコードが移り変わってゆく事で成り立っており、これを「コード進行」と呼びます。
YouTubeに合わせて弾いてると自動的にコードが移り変わってくれますが、それがない状態で弾くときは自分でコードの流れを表現する必要があります。
コードトーンを練習していると必然的にそれができるので、後ろで何も鳴っていなくても演奏に起承転結ができます。
感じた点②
指の動きが複雑。
今までアドリブを弾く時は「ペンタトニックスケール」だけで弾いていました。
この「ペンタトニックスケール」は、通称「ペンタ」と呼ばれ、ギターでアドリブをするならまずはペンタからと言われるほど定番のスケールです。
ペンタはギターの構造にとてもマッチした音の並びで構成されており、ある程度練習すればアドリブができてしまいます。
ですが、指の動きだけで演奏する癖がついてしまう面もあり理由①で紹介した流れのある演奏ができない要因にもつながってきます。
感じた点③
指板上の音名を意識するクセがつく。
ギターは良くも悪くも指のフォームで覚えることができる楽器です。
なので初めのうちは教則本に書いてある、コードフォームを見ながら練習する事になります。
ですが、フォームだけで覚えてしまうと指板上の音名がわからないので応用が効かなくなってしまいます。
僕自身何年もその状態が続いていて、今でも指板上の音を完全に把握しているわけではないです。
ですが、コードトーンを練習していると徐々に指板上の音名を意識するようになりました。
そうすると今までアドリブで弾いていたペンタも音名を意識するようになり、コードに合う音を追加したりすることができるようなります。
ちなみに現在練習しているのは、ジャズギタリストの「藤井進一」さんの下記のブログのエクササイズです。
今まで色んなコードトーンに挑戦しては挫折していましたが、この記事のエクササイズは今でも続けられています。
いつかレッスンも受けてみたいと思うくらいに参考になりますので是非!
動画はこちら